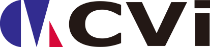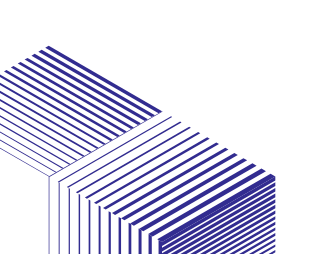勤怠管理システムとは?機能からメリット・デメリットまで解説
勤怠管理システムとは、従業員の出退勤や残業、休暇、欠勤などの管理をデジタル上で行えるシステムのことです。
そもそも、勤怠管理とは、会社が従業員の出勤時間や退勤時刻、労働時間、休暇の取得状況といった労働状況を記録・把握することをいいます。もし、適切でないことがわかれば、改善に向けて働きかける必要があります。
従来のタイムカードとExcelによる勤怠管理には、集計業務や申請・承認業務、法改正への対応が煩雑だったり、不正打刻を判別しづらかったりという課題がありました。このような課題を解消してくれるのが勤怠管理システムです。
このページでは、勤怠管理システムの種類や機能から、導入のメリット・デメリット、選定ポイントまでを網羅してお伝えします。
勤怠管理システムとは
勤怠管理システムとは、従業員の出退勤や残業、休暇、欠勤などの管理をデジタル上で行えるシステムのことです。
勤怠管理システムには、打刻機能やシフト管理機能、申請・承認(ワークフロー)機能などが基本機能として搭載されています。
勤怠管理システムの機能
ここで、勤怠管理システムの機能について詳しくご紹介いたします。
打刻機能
従業員の勤務時間を把握するために、出勤・退勤時刻を記録する機能です。
打刻方法は幅広く、タッチパネル式やICカード式など、さまざまな勤怠管理システムが提供されています。各自のPCやスマートフォンから打刻できるタイプもあります。
シフト管理機能
正社員とパートなどの雇用形態をふまえてシフト表を作成することができ、作業を大幅に効率化してくれるため、シフト制で勤務する従業員の多い職場で活用できます。
申請・承認(ワークフロー)機能
従業員が有給休暇や遅刻・早退、残業、打刻時間の修正といった申請を上げたら、管理者(上長)が承認を行うワークフローの機能です。
申請・承認業務を効率化することができます。
集計・分析機能
出退勤時の打刻から、それぞれの従業員の労働時間や休憩時間、有給休暇取得状況などが集計される機能です。
分析機能では、部門ごとの労働時間の比較を行ったり、長時間労働をしている従業員の分布を確認したりなど、労務管理に役立つさまざまな分析が可能です。
アラート機能
打刻漏れや休暇申請などがあった場合に、本人や人事担当者に知らせてくれる機能です。
あらかじめ基準となる労働時間などを設定しておくことで、必要なアラートを発することができ、長時間労働の抑制などに活用できます。
データ連携機能
人事管理システムや給与計算システムなど、ほかのシステムと勤怠管理システムのデータを連携できる機能です。勤怠管理システムによって連携方法や連携可能なシステムは異なります。
既存システムと連携ができることを前提に、連携先が多いものを選定する必要があります。
勤怠管理システムの種類
勤怠管理システムには、利用形態から見て大きく「オンプレミス型」と「クラウド型」の2種類があります。
オンプレミス型
オンプレミス型の勤怠管理システムは、自社でサーバーを用意し、そこに勤怠管理システムのソフトウェアをインストールして利用する形態です。
初期費用や運用費用などが高額になる傾向がありますが、その分、カスタマイズ性・自由度が高い点が特徴です。ハードウェアや機能、セキュリティ対策など、あらゆる面で自社の希望に沿った勤怠管理システムを実現できます。
クラウド型
クラウド型の勤怠管理システムは、ハードウェアやソフトウェアの用意も運用保守も、すべてベンダーに任せられるタイプで、勤怠管理システムをサービスとして利用できる形態です。
基本的に、オンプレミス型よりも初期費用・ランニングコストを低く抑えることが可能です。
その分、カスタマイズ性は低い傾向があるため、自社の勤怠やセキュリティポリシーなどに合った勤怠管理システムを選定する必要があります。
勤怠管理業務の課題
勤怠管理業務は、長時間労働を防止したり有給休暇の取得を推進したりするために重要な業務ですが、多くの企業で以下のような課題を抱えています。
集計業務が煩雑
人事担当者は、従業員が日々、打刻する出勤時刻・退勤時を元に、締め日の後で集計作業を行います。勤怠管理システムを導入していない場合、集計作業は手計算やExcelを利用したものとなることが多いでしょう。
しかし、これらの方法では、作業に時間がかかる上に、ミスが発生しやすくなります。
フレックスタイム制や時短勤務者がいたりすればなおさらです。
不正打刻を判別しづらい
集計は従業員の給与計算の元データとなるため、正確に行う必要があります。
しかし、そもそも打刻の段階で従業員本人や上司、同僚などによる不正があった場合、人事担当者ではその判断ができません。
打刻にタイムカードを利用している場合は、同僚が代わりに打刻したり、直行直帰の際に後から勤務時間を水増ししたりする不正が横行しやすくなります。
勤務管理表の保管が煩雑
改正労働基準法により、勤怠データ関連記録の保存期間が3年から5年間へと延長されました(ただし、経過措置として、当分の間は3年が適用されます)。
保存対象の書類には、タイムカードや出勤簿、勤怠管理表などが含まれます。
アナログな方法で勤怠管理を行っている場合は、これらを紙で保存しておかなくてはならず、ファイリング作業など保管業務が煩雑になりますし、保管場所も確保しなくてはなりません。
申請・承認業務が煩雑
タイムカードの打刻忘れや、有給休暇取得のためなど、勤怠管理業務では申請・承認も発生します。
書類で申請し、決裁者に回覧しながらハンコで承認していく方法だと、書類がどこにあるかを把握しにくい上に、紛失の恐れもあります。人事担当者は、期日までに承認されるように取り計らいたいところですが、リアルタイムに把握できないため、業務がスムーズにいきません。また、申請者からの問い合わせに対応することも困難です。
法改正への対応が煩雑
労働基準法など、勤怠管理にまつわる法令が改正された場合、人事担当者はその都度、改正点を覚えて業務を変更しなくてはなりません。しかし、人事担当者の抱える業務はほかにもたくさんあり、法改正への対応だけに時間と労力をさくわけにはいきません。
かといって、違反すれば罰せられる恐れがあるためミスも許されず、業務負担が増加します。
勤怠管理システムの
メリット・デメリット
勤怠管理システムを導入することで、上記のような課題を解決できるのでしょうか?
まずは、勤怠管理システムを導入・活用するメリットとデメリットを確認していきましょう。
勤怠管理システムのメリット
勤怠管理システムの導入によって、「不正打刻や改ざんを防止できる」「従業員の労働時間の正確な把握が可能になる」などのメリットが期待できます。
不正打刻や改ざんを防止できる
タイムカードによる打刻は、他人のなりすましによる打刻や、定時で打刻して残業したりといった不正が起きやすい方法です。また、管理者や人事・経理担当者が残業時間を実際よりも少なく改ざんするといったことも起きやすくなります。これは、タイムカードには客観的な記録として残しにくい性質があるためです。
勤怠管理システムでは、それぞれの従業員が異なるアカウントでログインして打刻するため、なりすましによる打刻は起きにくく、また、複数の担当者が確認可能な客観的なデータとして記録が残るため、タイムカードに比べると改ざんなども起きにくくなります。
従業員の労働時間の正確な把握が可能になる
勤怠管理システムでは、出勤・退勤の打刻から正確な勤務時間を自動で計算してくれるため、人手による集計のような入力ミスや見間違い、計算ミスなどを低減できます。また、計算スピードも速いため、労働時間をリアルタイムに把握することができるようになります。
法改正に対応しやすい
勤怠管理システムの多くは、ベンダーが法改正に対応するため、人事担当が法令の改正点を詳しく把握していなくても、改正前と同様に利用しているだけで法改正に対応できます。
これにより、対応漏れによる罰則の心配をしなくて済むようになります。
リモートワークや支社などの勤怠を管理しやすい
コロナ禍の影響もあり、リモートワークを導入している企業もあるでしょう。また、本社以外に支社・営業所など複数の拠点を持つ企業も少なくありません。
このように、人事部門のある本社などのオフィスから離れたところで従業員が就業する場合、従来のタイムカードでは勤怠管理が行えません。
勤怠管理システムがあれば、自宅やサテライトオフィス、支店などから勤怠管理システムへアクセスして打刻や申請が行えるため、オフィスから離れたところにいる従業員の勤怠管理もしやすくなります。
正確な給与計算が可能になる
給与計算システムとデータ連携できる勤怠管理システムを導入・活用していれば、勤務形態に合わせて給与計算を自動計算することができます。
その結果、給与の計算ミスやごまかしなどが起きづらくなり、従業員との信頼関係の向上が期待できます。
コンプライアンスの強化が可能になる
勤怠管理システムでは、勤務時間や残業時間、深夜や休日の割り増しなどが正確に計算されるため、雇用者側で残業代の不払いといった不正が起きにくくなります。
また、最新の法令に準拠した勤怠管理システムを利用することで、法改正にもスムーズに対応できます。最近では、2019年4月より順次施行された働き方改革関連法により、残業時間の上限が残業時間原則として月45時間・年360時間までと定められました。こうした変更に自力で対応するのは大変です。
勤怠管理システムを活用することで、コンプライアンスの強化が可能になり、クリーンな企業として社内外のイメージ向上にもつながります。
勤怠管理システムのデメリット
一方、勤怠管理システムの導入にもマイナスポイントが存在します。
それが、導入に金銭コストがかかる点です。
無料かつ無期限で利用できる勤怠管理システムもたくさんありますが、利用人数や機能に制限が設けられており、小規模な企業でもない限り、実用的ではありません。
また、勤怠管理は重要ではあるものの、営業ツールのように直接的な利益を生み出すものではないため、予算確保のための稟議が通りにくい面もあります。
勤怠管理システムの導入によって、自社の勤怠管理におけるどのような課題が解消できるのか、それによってどれくらいコスト削減が可能なのかを試算して経営層を説得する必要があるでしょう。
勤怠管理システム導入の失敗例
勤怠管理システムの導入には多くのメリットが期待されますが、失敗事例も少なくありません。以下は代表的な失敗例です。
会社の規模や勤務形態に合わなかった
勤怠管理システムは、会社の規模や勤務形態に応じた選定が必要です。小規模企業が大企業向けのシステムを導入すると、機能を使い切れない一方で、大企業が中小企業向けシステムを採用すると、変形労働制やシフト制、裁量労働制などの複雑な管理に対応できない場合があります。結果として、システムの乗り換えが必要になることもあります。
機能を使いこなせなかった
高機能なシステムを導入しても、社員が使いこなせなければ意味がありません。十分な講習が行われなかったり、マニュアルが不十分だったりすると、システムが社内に浸透せず、活用されないまま放置されるケースがあります。
勤怠管理システム導入の失敗を防ぐには、自社の規模や勤務形態に合ったシステムを選び、従業員が使いやすい環境を整えることが重要です。さらに、既存のシステムとの連携を確認し、信頼性の高いサポート体制を備えた勤怠管理システムを選びましょう。
【関連記事】
勤怠管理システムの
選定ポイント
多様な勤務形態に対応しているか
働き方改革の影響もあり、現在の日本では、フレックスタイム制やリモートワーク、時短勤務など、さまざまな勤務形態が見られるようになりました。
こうした一律ではない勤務形態にも対応できる勤怠管理システムが求められます。
たとえば、自席でPCからも打刻できたり、自宅でスマートフォンから打刻できたり、シフト勤務者や時短勤務者の休憩時間の計算も適切に行われるなど、多様な勤務形態に対応した勤怠管理システムを導入する必要があるでしょう。
最新法令に準拠しているか
労働基準法を中心に、勤怠管理において重要な法令が改正された場合、それに準拠した勤怠管理システムを利用することが、勤怠管理においてミスを減らしたり業務効率化を実現したりする上で重要になってきます。
たとえば、働き方改革関連法が2019年4月より順次施行され、雇用者側に年間で5日以上の年次休暇を取得させる義務が課せられました。こうした法改正に準拠していれば、期末が近づいてもまだ5日間の年次休暇を消化していない従業員をアラートで知らせるなどの活用が可能になり、法令違反を防ぐことができます。
外国語に対応できるか
日本では少子高齢化により、労働人口が減少しており、今後もますます人手不足が進むことが予測されます。不足している労働力を補うために、外国人労働者を受け入れている企業は少なくありません。
外国人労働者に勤怠管理システムをスムーズに利用してもらうためには、外国語に対応できる勤怠管理システムを選ぶ必要があります。特に、日本語を読むことができない外国人労働者が多い場合には必須です。
他システムとの連携ができるか
勤怠管理システムには、出勤日数や労働時間、残業時間などのデータが蓄積されます。
これらは、勤怠管理において重要なデータであることはもちろん、給与計算や人事管理といった業務でも活用できます。
勤怠管理システムのほかにも給与計算システムや人事管理システムを導入・活用している場合は、個々の部門でそれぞれデータを作成したり入力したりするのではなく、いずれか最初に作成されたデータをインポートして利用できると、業務効率化につながります。
後から新たなシステムを導入することも見越し、多くの連携先がある勤怠管理システムを選ぶと良いでしょう。
自社のシステム利用形態に適合するか
ここ数年来、オンプレミス型ではなくクラウド型の勤怠管理システムを選ぶ傾向が強くなってきています。とはいえ、カスタマイズ性の問題や自社のセキュリティーポリシーとの適合性の観点から、クラウド型の導入に二の足を踏むケースもあるかもしれません。
ただし、なかには、たとえばCViが提供する「CViElite Attendance」のように、クラウド型でありながらカスタマイズ性が高く、且つ高度なセキュリティレベルを実現している勤怠管理システムもあります。
システム利用開始後の運用保守の容易性や費用対効果も含めた総合的な観点から、自社の利用形態に適合するシステムを選ぶ必要があります。
このほか、操作性の高さや打刻・申請漏れへの対策があることなども重要な選定ポイントとなります。
勤怠管理システムの選定ポイントについて詳しくは、下記ページもご覧ください。
【関連記事】
働き方改革に対応した勤怠管理の方法について
働き方改革の成功にも、適切な勤怠管理システムの導入が重要です。 テレワークや時短勤務に対応するために、スマホを利用した勤怠打刻や柔軟なスケジュール管理が可能なシステムが効果的です。
また、勤怠データを分析することで、従業員の業務状況を可視化し、業務効率化や改善策を講じることができます。
さらには、テレワークの普及に伴い勤怠データの管理がますます重要になってきていますが、システムの活用により、リアルタイムでの勤務時間や休暇の記録・共有が可能となります。
このように、適切な勤怠管理システムの導入と運用が、働き方改革を推進するための鍵となります。
【関連記事】
勤怠管理システムのセキュリティについて
勤怠管理システムのセキュリティ対策は、個人情報の保護や業務の継続性を確保するために不可欠です。
まず、勤怠管理システムには従業員の氏名、役職、所属、勤怠情報など、非常に機密性の高いデータが含まれています。
これらの情報が外部に漏洩すると、企業の信用が失墜し、顧客や従業員との信頼関係が損なわれるだけでなく、法的な制裁や賠償金の発生といった大きな影響を受ける可能性があります。日本では個人情報保護法により、適切な個人データ管理が義務付けられているため、堅牢なセキュリティ対策が求められます。
また、不正アクセスのリスクも見過ごせません。セキュリティが脆弱なシステムは、外部からのサイバー攻撃を受けやすく、データの改ざんや削除、さらには悪意のある利用が行われる可能性があります。
これにより、給与計算や人事手続きが遅れるなど、業務全体が混乱する恐れがあります。さらに、勤怠データが改ざんされると、正確な給与計算や労働時間の管理ができなくなり、企業と従業員間でトラブルが発生するリスクが高まります。給与計算のエラーは、税務処理や社会保険の計算にも影響を及ぼし、企業のコンプライアンス違反につながる恐れがあります。
このようなリスクを回避し、勤怠管理システムを安全に運用するためには、効果的なセキュリティ対策を講じることが必要です。セキュリティを強化することで、従業員データの保護と業務の継続性が確保され、企業の信頼性向上にもつながります。勤怠管理システムは業務効率化の鍵となる一方で、その安全性を確保することが、企業の持続的な成長を支える重要な要素であるといえるでしょう。
【関連記事】
勤怠管理システムの導入手順について
勤怠管理システムの導入は、業務効率化や正確な勤怠データ管理を実現するために重要です。しかし、導入を成功させるには適切な手順を踏むことが不可欠です。以下に勤怠管理システム導入のステップをまとめました。
1.勤怠管理システムを導入する目的を明確化する
2.勤怠管理システムの種類を選ぶ
3.勤怠管理システムを選定する
4.選定した勤怠管理システムの機能・操作方法を全社員に共有する
5.選定した勤怠管理システムを試運用する
6.問題なしと判断したら本格的導入を決定する
勤怠管理システム導入の成功は、事前の準備と適切な手順にかかっています。明確な目的設定と段階的な実施を心がけ、自社に最適なシステムを選定しましょう。
【関連記事】
まとめ
勤怠管理システムは、タイムカードやExcelを使用した従来のアナログな勤怠管理方法が抱えていた、打刻や業務効率の低さといった課題を解消するのに役立ちます。
勤怠管理システムを選ぶ際は、多様な勤務形態に対応しているか、最新法令に準拠しているか、会社のセキュリティ基準を満たしているか、外国語に対応できるかといったチェックポイントを確認し、自社にマッチしたものを導入しましょう。